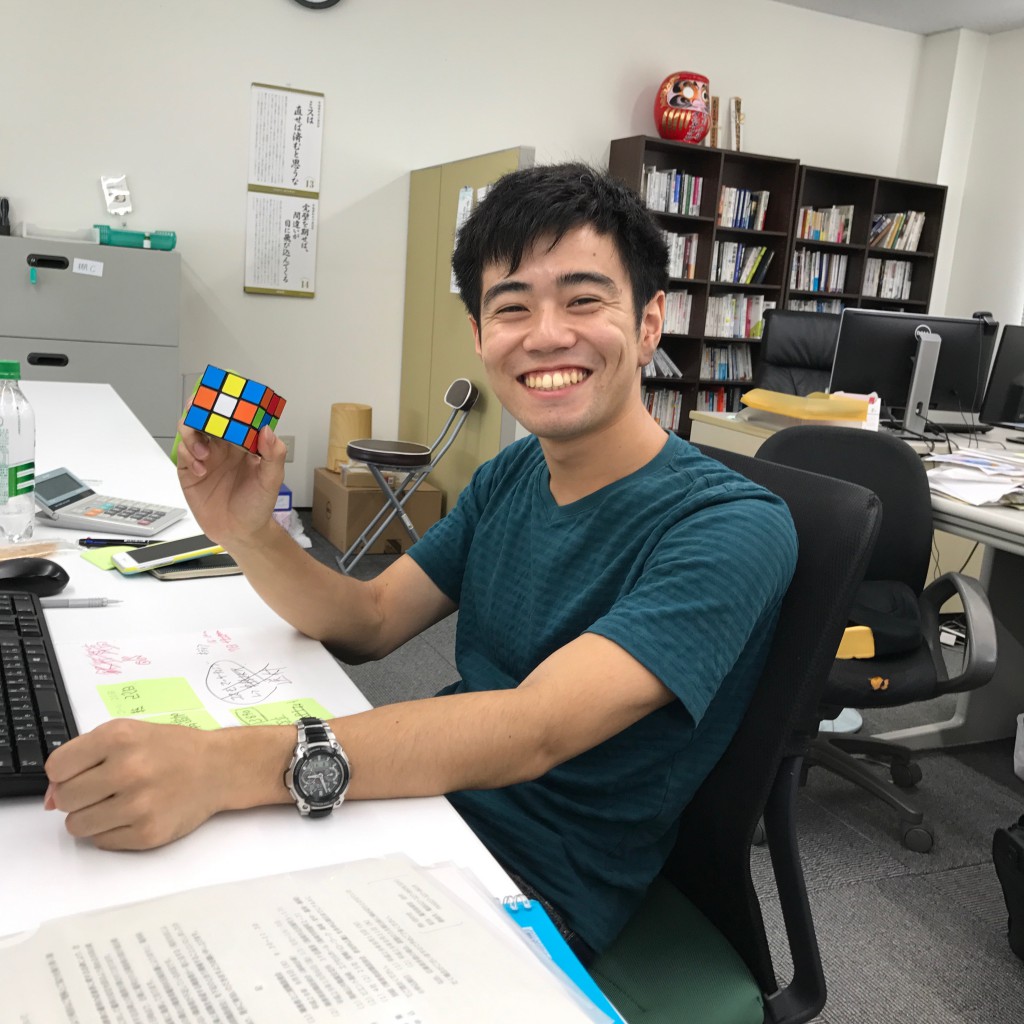金田です。
インターゾーンのサービスを紹介しつつ細かな問合せを吸い上げるべく、
新しいメールマガジン(?)をお客様にお届けすることになりました。
本日、その記念すべき第1号を送信したのですが…
このメールの発行者である「タカハシ君」の自己紹介がおもしろいので、まるっと転載しちゃいます。
////////////////////////////////
◆◆ (1)私、高橋の自己紹介!
◇◇◇________________________________
ご挨拶遅れましたが、私、高橋能成(よしなり)と申します。
中央大学卒業後、インターゾーンの営業部で活動をしていました。
北海道・東北・関東・新潟・北陸・四国エリアをメインで担当させていただき、
100社以上の業績アップ支援、業務改善支援を行ってきました。
おかげさまで全国各地へ出張させていただいておりました!
そんなある日・・・・
北海道へ向かう最終便の飛行機の上空で「 ガンッ!! 」と、
突然の激しい頭痛に襲われました。
気が付いたらCAに体を激しく揺すられていました。
周りを見渡すと、既に着陸していて乗客は1人も居ません。
立ち上がろうとしたのですが、立てない・・明らかに身体がおかしい・・
救急車を提案されましたが、「明日は札幌で大切な打合せがある!」と、拒否。
2時間ほどで立てるようになったのですが、上手く歩けない・・
必死の思いで札幌のホテルへ。死を覚悟して寝たのをよく覚えています。
その後は滞りなく?1週間ほど仕事をしていたのですが、
あまりにも体調不良が続くので群馬の田舎の病院へ。
医師に事の経緯を話すと「本気で言っているのか!?」と、怒られました。
検査をすると・・・
10万人に1人しかいないという、珍しすぎる先天性の脳血管腫瘍が発見されました。
「とりあえず群馬の大きな病院に行きなさい!」と救急車で運ばれました。
しかし、群馬の大きな病院では「初めて見た・・群馬で手術はできない」と、
埼玉の病院に運ばれました。
埼玉の病院では「あと5年、生きられるかどうか・・・」と、宣告されました。
「開頭手術を行えば大丈夫!」との事で、手術成功率は70%でしたが、
一昨年3月に、15時間に及ぶ開頭手術から生還してまいりました!
以上のことがあり、一昨年3月から休職をいただいていましたが、
両親を始め、社内サポート・友人、そして取引先企業様からいただいた
温かいエールが大きな力となり、先月4月より復職させていただきました!!
突然のことでご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ございませんでした。
再び全国各所に出張し、全力でサポートさせていただきたいのですが、
現在はドクターストップ・・・ということで、微力ではございますが、
このメールマガジンでホットな情報をお届けしたいと思います!
ホームページやコールセンターに関すること等々、ご質問やご相談も
お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします!
////////////////////////////////
ということで、タカハシ君の力作です!!
さっそく、この内容についてのご返信が何通も届いております。ありがとうございます。
ちなみにタカハシ君は、復帰後にキックボードで通勤していたところ転んで足を骨折するという事件も起こしております。
(これは誰もフォローできない…!)
そんな彼も、5月から新しく発足した「新クライアントユニット」のカタチを作り上げるべく頑張っています。
私の「こーゆー息子が欲しいランキング」のトップを独走するくらい、優しいオトコです。
これからのメールマガジンにも期待です!

似顔絵…あんまり似てなくてごめんよ、たかはしクン。